内窓・二重窓リフォームしたら、結露対策になると聞いていたのに、内窓設置後にも結露が発生してしまっていて、後悔しているという方は少なくありません。
そもそも結露は、外気温に室内の温度が急激に冷やされることで起きる現象です。そのため、内窓を設置したからと言って、必ずしも結露対策になるとは限らないという落とし穴があります。
そこでこの記事では、内窓リフォームしても結露が発生する際に考えられる要因をはじめ、内窓の結露を防ぐ方法、さらには結露対策におすすめな内窓を徹底解説していきます。
窓に結露が発生する理由

冒頭でも軽く述べましたが、結露は外の冷気と室内の温度差があればあるほど、なおかつ空気中の水蒸気の量によって、発生しやすくなります。
窓ガラスに結露が発生しやすいのは、壁などと比較して、ガラス自体が薄く、熱を伝導しやすいためです。
特に冬などの気温が下がる時期や、梅雨などの湿度の高い時期などに結露が発生しやすい傾向があります。
そのため、結露を防ぎたいと思ったら、部屋の湿度を高くしすぎない工夫や、窓ガラスを介して、室内の空気が冷やされすぎないように、内窓・二重窓を設置するなどといった断熱対策を講じる必要があるのです。
結露を放置しておくと危険

結露自体は珍しい現象ではないので、そこまで敏感にならず、気にしていないという方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、結露を甘く見てはいけません。結露をそのままの状態で長期間放置しておくと、色々な危険があることをご存知でしたか?
結露対策に、内窓・二重窓リフォームがおすすめであるというのも、結露には様々な危険が存在しているからです。
ここでは、結露を放置しておく危険な理由を3つご紹介していきますので、必ず目を通してください。
- 住宅の寿命が縮む
- 機械の故障を引き起こす
- カビなどにアレルギー反応を起こす
住宅の寿命が縮む
結露を放置しておくと、特に木材に大きなダメージを与えてしまうと言われています。
サッシをはじめ、床や柱など、木材を要所要所で使用している住宅においては、発生した結露が繰り返し木材に染み込むことで、木材自体の強度が弱まってしまい、ひび割れなどが起こる原因となりかねません。
木材がひび割れてしまったら、家の耐震強度などにも影響が出てくることもあり、非常に危険です。修繕や、時には大々的なリフォームが必要となってしまうことがあるので、長く住み続ける前提の住宅では、結露は大敵だということを頭に入れておきましょう。
機械の故障を引き起こす
結露が発生している場所の近くに、電源やケーブルなど、様々な電子機器がある場合には、感電の原因となったり、繋がっている機器の故障を引き起こしたりしてしまう可能性もあります。
現代では、電子機器なしの生活はほぼ考えられない上、もし故障してしまったら、修理や買い替えなどにお金がかかってしまいます。
カビなどにアレルギー反応を起こす
特に小さなお子様がいらっしゃる場合には、結露によって誘発されたカビにより、アレルギー反応やシックハウス症候群を起こしてしまうことが懸念されます。
その上、カビが発生してしまうと、カビ臭くなり、室内の居心地も悪くなることは必至です。
つまり、結露を放置していると、住環境が著しく悪化する原因となるのです。
結露対策におすすめな内窓リフォーム
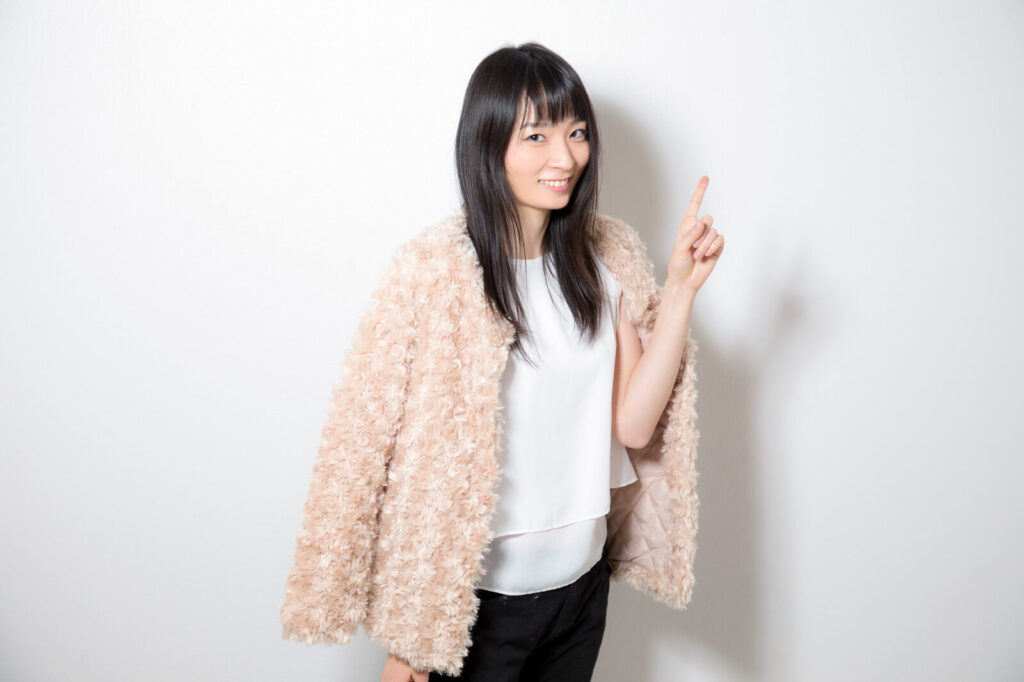
結露の発生の原因や、結露を放置しておくと危険であることを理解したところで、結露対策におすすめな内窓・二重窓リフォームについて、今一度振り返っておきます。
内窓リフォームとは、既存の窓の内側に、別途新しい窓を取り付けることです。
内窓リフォームは、既存窓枠を生かして施工できるため、比較的安価かつ施工スピードも早く、手軽なリフォームであると言われています。
その上、結露対策はもちろんのこと、高い断熱効果や防音効果、防犯対策、災害対策など、様々な効果があるので、近年ではとても高い人気を誇るリフォームです。
既存窓の他にもう1つ窓が付くことで、外と室内の温度が伝導しにくくなるため、結露対策になるとも言われています。
内窓リフォームしても結露が発生する場合に考えられる要因

せっかく結露対策になると思って一念発起し内窓・二重窓リフォームしたのに、結露が発生してしまって困っているという場合に、考えられる要因を6つピックアップしました。1つずつ見ていきましょう。
- 寒冷地である
- 既存窓と内窓の距離がありすぎる
- 単板ガラスである
- アルミサッシである
- ペアガラスの劣化
- 気密性が低い
寒冷地である
そもそも、結露対策を行いたいと思っていたということは、もともと既存窓に発生してしまう結露に悩まされていたのではないでしょうか。
前述した通り、窓に発生する結露は、外の冷たい空気に、室内の暖かい空気が急速に冷却されることで発生します。
これを防ぐために内窓を設置することになるのですが、北海道や東北地方といった寒冷地の場合には、内窓を設置したところで、冬の外気温が低すぎて、あまり意味がないことがしばしばあるのです。
もし、お住まいの地域が寒冷地であるということであれば、内窓を設置するだけでは、結露対策にはならない可能性があるということを今一度押さえておいてください。
不安な方は、内窓の設置する前の見積もり段階で、業者に結露対策になるかどうかをきちんと確認しておくと良いでしょう。
既存窓と内窓の距離がありすぎる
既存窓と内窓の距離が空きすぎると、既存窓と内窓の間にできる空気の層が期待より断熱効果を発揮しないことがあり、結露が発生しやすくなってしまうことがあります。
こうした場合には、既存窓と内窓の距離を近づけ、より気密性を高めることで結露の発生を予防することができるかもしれません。
ただし、防音効果を高めるには、逆に既存窓と内窓の距離が空いていた方が良いとされているため、既存窓と内窓の距離を狭めることで、防音効果は少し弱まってしまう可能性があります。
単板ガラスである
せっかく内窓を設置しても、内窓のガラスが単板ガラスである場合には、あまり高い断熱効果が期待できず、結果的に、既存窓と内窓の間の空気層もあまり機能せず、結露対策にならないことが予想されます。
あまりこのパターンは少ないとは思いますが、仮に単板ガラスを選んだというのであれば、内窓を複層ガラスに交換してみると、断熱効果が高まり、同時に結露対策にもなるかもしれません。
アルミサッシである
これも稀なパターンかと思いますが、内窓のサッシがアルミ製であるならば、熱の伝導率が高く、結果的に、内窓に結露が発生しやすい要因となっている可能性があります。
内窓リフォームする時点で、一般的には樹脂製のサッシのものを選ぶことになるはずとは言え、なんらかの理由で、仮にアルミ製のものを選んでしまっていたという場合には、樹脂製のサッシに交換すると気密性が高まり、なおかつ熱伝導率も低くなるので、結露対策になるでしょう。
複層ガラスの劣化
既存窓あるいは内窓、あるいは両方が複層ガラスであっても、複層ガラス自体が経年で劣化してしまい、複層ガラスを構成している2枚のガラスの間の空気層の断熱効果が薄れ、結露が発生しやすくなってしまうこともあります。
さらに、複層ガラスの内部にも結露が発生してしまい、見栄えが悪くなることも起こり得ます。
こうした自体が起きてしまったら、自分でどうこうできるものではないので、ガラス自体を交換するなどといった対策を講じるしかありません。
気密性が低い
内窓を設置しても、内窓自体の不良をはじめ、施工不良や、既存窓枠の歪みなど、様々な要因で、気密性が低くなってしまっている場合にも、断熱効果が薄れ、結露が発生する原因となります。
内窓を設置した直後からこの状態であれば、施工業者に一度問い合わせてみて、施工不良がないかや、実は既存窓枠が歪んでいて隙間がないかなど確認してもらい、可能であれば、改めて設置し直してもらうなどすると良いかもしれません。
内窓に発生する結露を防ぐ方法

内窓・二重窓リフォームしたのに、結露が発生する際に考えられる要因を理解したところで、内窓に発生する結露を防ぐ7つの方法についてもご紹介していきます。
- 内窓と既存窓の間の換気を行う
- 室内の換気を行う
- 断熱シートを貼る
- 結露防止シートを貼る
- 結露防止スプレーを使用する
- 改めてリフォームする
- 窓ガラスを交換する
内窓と既存窓の間の換気を行う
結露が発生する要因としては、外気温と室内気温の温度差だけでなく、空気中に含まれる水蒸気の量も関係してきます。
そのため、定期的に内窓と既存窓の間の換気を行い、内窓と既存窓の間の湿度を下げることで、結露対策になる場合があります。
具体的には、日中の短い時間(10分程度)内窓は閉じたまま、既存窓のみ開け放すという簡単な方法です。
室内の換気を行う
室内の湿度自体が高いという時には、内窓と既存窓の間の換気だけでなく、内窓も開け、他の別の窓も開けて、空気の通り道を作り、室内自体の湿度を下げるということでも、結露対策になる場合があります。
断熱シートを貼る
断熱シートとは、窓ガラスをはじめ、床などに貼ることで、暖房効果を高めることができるシートのことです。
窓用の断熱シートには、気泡緩衝材タイプのものや、プライバシーを守ることができる模様が入ったもの、UVをカットできるものなど、色々な種類があります。
この断熱シートを、既存窓や内窓に貼り付けることで、断熱効果を高め、結露の発生を抑えることができる場合があり、ネット通販などで簡単に手に入れることができるので、試してみる価値はあるかと思います。
また、剥がしやすいものを選べば、賃貸物件や、マンションであっても安心して使用できるでしょう。
結露防止シートを貼る
結露防止シートとは、その名の通り、窓ガラスに貼ることで、断熱効果を高め、結露対策を行うことができるシートのことです。
断熱フィルムタイプの場合には、窓ガラス全体に貼ることになりますが、プチプチに空気の層があるものを選ぶと、断熱効果がより高くなり、高い結露対策になると言われています。
一方吸水タイプのシートの場合には、窓の下部分のみに貼り付けることになりますが、結露が発生する前提で貼るので、結露を防止するというよりは、結露で発生した水を吸い取るという効果しかありません。
いずれにせよ、手軽に結露対策することができるとはいえ、窓の見栄えが悪くなるというデメリットがあります。
結露防止スプレーを使用する
結露防止スプレーとは、スプレーで結露防止効果のある液体を窓ガラスに吹きかけることにより、膜が薄く張られ、水分を弾いたり、吸収したりする効果を発揮し、結果的に窓に発生する結露を軽減することができるものです。
こちらも、結露の発生を防ぐというよりは、ある程度結露が発生してしまう前提で、発生した結露を軽減するイメージです。
結露防止シートとは異なり、窓ガラスの見た目を損なうことがない上、すりガラスなど様々な素材にも使用できるものがあり、簡単に使用できるというメリットがあります。
改めてリフォームする
内窓を設置した直後ではなく、ある程度年月が経過してから結露に再び悩みはじめたという場合には、改めてリフォームするという手もあります。
予算さえあれば、内窓と既存窓の距離を狭めたり、ほんの少しの窓枠やサッシの隙間を埋めたりという小さなものから、いっそ内窓や既存窓自体取り替えてしまうといった大胆な方法まで、業者と相談しながら最適な方法を選ぶことができるでしょう。
窓ガラスを交換する
もし既存窓あるいは内窓が単板ガラスであったり、複層ガラスであっても、劣化してしまっていたりするならば、窓ガラスのみを交換してしまうというのも1つの手段です。
複層ガラスあるいは真空ガラスなどにすることで、より高い断熱効果が期待でき、結果的に結露対策にもなるでしょう。
結露対策におすすめな内窓

これから結露対策のために内窓・二重窓をリフォームしようと考えている方、あるいは内窓リフォームに失敗してしまったから、改めて内窓を取り替えたいという方のために、結露対策におすすめな内窓をご紹介します。
Low-E複層ガラス+樹脂サッシ
Low-E複層ガラスとは、ガラスの表面に、酸化錫や銀などといった特殊な金属の膜をコーティングしたガラスを2枚重ね、間に空気の層を有するものを言います。
特殊な金属の膜をコーティングすることにより、太陽から発せられる熱や、室内の暖かい熱を吸収および反射し、結果的に高い断熱効果を発揮するのです。
一般的な複層ガラスよりも、金属膜がある分、より高い断熱効果を得られるということは、より高い結露対策になると言っても過言ではありません。
加えて、熱伝導率が低く、高い気密性を発揮する樹脂製のサッシを組み合わせた内窓を設置すれば、安心できるでしょう。
まとめ
内窓・二重窓リフォームしても結露が発生する際に考えられる要因について、この記事では、内窓の結露を防ぐ方法、さらには結露対策におすすめな内窓を徹底解説してきました。
本来、内窓リフォームで最も得られる効果は、断熱効果であり、お住まいの地域など様々な要因により、結露対策はそこまで得られないことがあることを忘れてはいけません。
しかし、それでも、様々な対策を講じれば、時に期待通りの結露対策になることもあるので、すぐに諦めてしまうというのも少し勿体無いと言えます。
この記事を参考に、内窓に結露が発生してしまう際にも、様々な対策を行ってみるなどして、少しでも、結露の発生を予防できることを願っています。


